ご祭神
大山咋命(おおやまくいのみこと)
由緒
「日吉社」は滋賀県坂本の「日吉大社」と同一御祭神で、比叡山延暦寺の守護神です。全国の山王さんと呼称される日枝神社、日吉神社、松尾神社など同じ御祭神をお祀りしています。
近隣の院林・広安・寺家と柴田屋の四カ村は、鎌倉時代以降、石黒の庄、院林郷に属していたこともあり、何れの氏神神社も御祭神は同じで「日吉社」です。

御神徳は土木の知識に優れ、開拓の祖神(おやがみ)として崇(あが)められています。またお酒を造ることに長けていたため、酒造業、酒店、酒飲業者の繁栄を願い敬(うやま)われるほか、縁結びの神としての信仰が厚いとされています。
明治以前は神仏混合の時代であり「山王権現」と敬われましたが、明治4年(西暦1871年)に廃仏希釈(はいぶつきしゃく)が実施され、神社「日吉社」として「村社」の社格を得ました。戦後昭和21年(西暦1946年)宗教法人法に基づき「宗教法人 日吉社」として受け継がれ現在に至っています。
また神社の創建年代は不詳となっていますが、氏神様祠(ほこら)の設置時期を推測すると、戦国時代に居城が滅ぼされた後(※別記「柴田屋古館跡」参照)西暦1600年前後の時代、この場所は廃墟であったと思われます。その後柴田屋村が改作された承応3年(西暦1654年 ※別記「柴田屋村について」参照)頃、その後そう遅くはない時期であると考えられます。
本殿は総欅(そうけやき)造りですが何時頃の建造物か定かではありません。旧拝殿(※後述の倒木による倒壊前)は文政7年(西暦1824年)から8年にかけて建設された建物だったので、それより新しい事からその後しばらくしてから建てられたものと推測されます。
この旧拝殿は平成16年(西暦2004年)に発生した台風23号の強風により、本殿横にあった樹木が倒伏し倒壊。その後間もなく拝殿復興委員会が設立され、平成18年(西暦2006年)には本殿と繋がった新拝殿が完成し現在に至っています。
境内社
◇ご祭神
豊受姫大神(とようけひめのおおかみ)
◇由緒
御祭神は豊受大神宮(伊勢神宮外宮)に奉祀される豊受大神として知られており、食物・穀物を司る女神様をお祀りしています。
建物の建築時期や経緯などについては伝えられていませんが、砺波平野は神明社が多い地域であり、これは江戸時代に加賀藩による新田開発を進めるにあたり、信仰政策の一環として神明社の信仰を奨励したことなどによるもので、柴田屋日吉社においても境内社として神明社を祀ることになったのではないかと推測されます。
◇ご祭神
弥都波能売大神(みずはのめのおおかみ)
◇由緒
御祭神は日本における代表的な水の神様(水神)ですが、その由来は元々西に大きく蛇行していた旅川は、安政3年(西暦1856年)に行われた改修工事により現在のように南から北へ真っ直ぐ流れるようになりました。その際に川の跡地に水天宮として祠を祀り、以来「掘り変えの宮」として長く親しまれてきました。
その後、昭和38〜48年(西暦1963〜73年)にかけて圃場整備事業が実施され、その折に現在の場所(日吉社境内)に移築されたものです。
南砺市史跡指定文化財「柴田屋古館跡」
「柴田屋古館跡」として南砺市史跡指定文化財となっています。永禄年間(西暦1560年頃)、越中新川郡松倉村(現在の富山県魚津市)の松倉城主・椎名肥前守康胤(しいなひぜんのかみやすたね)の家臣、柴田丹後守久光(しばたたんごのかみひさみつ)が居住し、蓮沼城(石動)の出城として築かれました。天正7年(西暦1579年)に、貴船城(福岡・福光城石黒氏の出城)主、石黒左近蔵人(いしくろのさこんくらんど)に攻められました。世は戦国時代、一向一揆の最中、その前に松倉城は上杉謙信に攻められ廉胤は難を逃れ蓮沼城に移りましたが、天正4年(西暦1576年)に蓮沼城も落城しました。孤立してしまった久光は、石黒氏に攻められ滅んだとされています。
境内は広く樹齢4~5百年を数える大木が数本残っており、社殿の辺りは小高く土塁は当時の面影が偲ばれます。また明治44年(西暦1911年)には石垣が積まれるなど、神社の境内として整備が進められてきました。

パンフレット


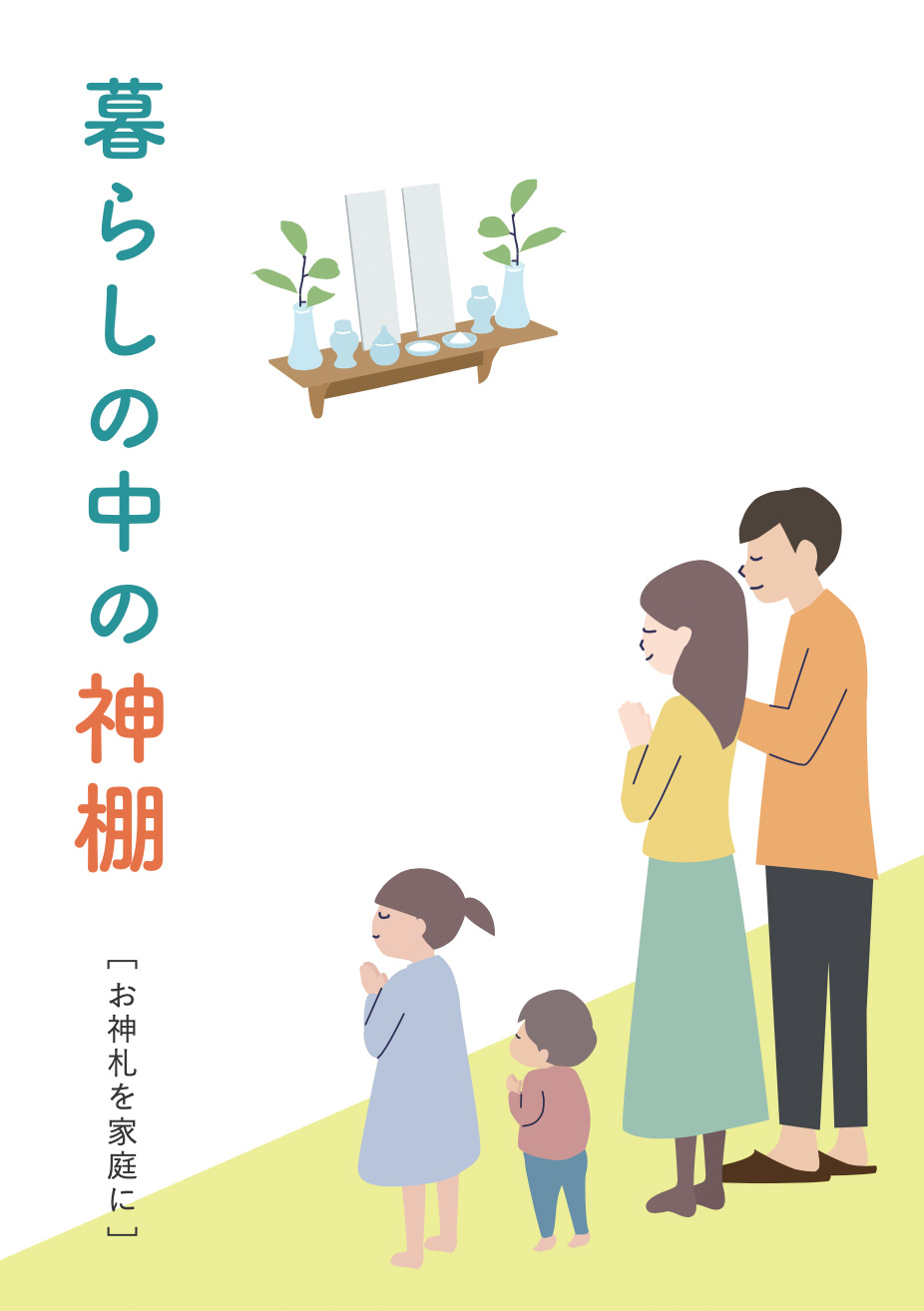 暮らしの中の神棚
暮らしの中の神棚 神社総代のすゝめ
神社総代のすゝめ